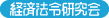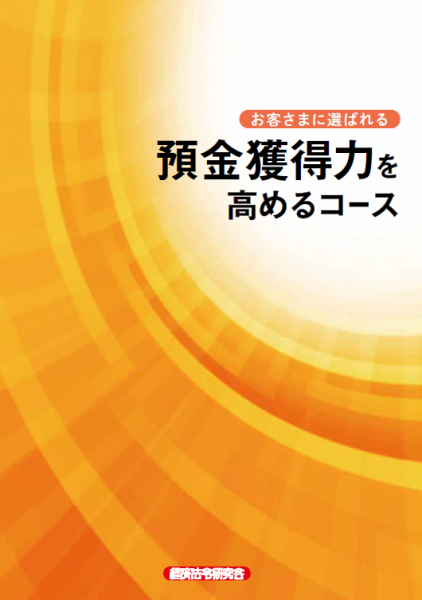1.金融機関の基本ビジネスモデルを見直す時
金融機関の収益源は、大きく分けて「預金」「融資」「手数料・役務収益」の3本柱で構成されています。
なかでも預金は融資の原資であると同時に、余資運用面においても金融機関自身の収益源として欠かせない存在です。
つまり、「預金を集め、融資で運用し、残った資金を他で運用する」ことこそ、金融の根幹ともいえるビジネスモデルなのです。
2.長い“ゼロ金利時代”がもたらした変化
2024年まで続いたゼロ金利・マイナス金利政策の影響で、多くの金融機関は積極的に預金を推進してきませんでした。
しかし、現在は金利が上昇し、
・融資利率の上昇による収益性向上
・余資を日銀当座預金に預けても利息がつく状況
となり、金融機関が再び「預金を持つことのメリット」が高まりました。

一方で、資産運用の多様化による他の金融商品等への振替えや高齢化による相続流出など、預金が減少しやすい環境にもなっています。
3.「預金を持つほど強くなる」地域金融機関
地域金融機関にとって、最も大きな収益源は貸出利息です。
金利上昇局面では、潤沢な預金を持つほど、より多くの融資を行い、収益拡大につなげることができます。
その意味で、今こそ「預金をいかに確保できるか」が、地域金融機関の競争力を左右するポイントになっているのです。
4.預金推進のカギは「動機」と「タイミング」
預金推進では、新規口座開設・生活口座の獲得・将来に備えての預金提案など、多様なアプローチが求められます。
なかでも重要なのが、お客さまの“動機”や“需要”をどう喚起するかです。
例えば──
・結婚・出産・住宅購入といったライフイベント
・退職・相続・転勤などの人生の節目
こうした「預金ニーズが生まれる瞬間」を捉えることが、成果を左右します。
ただし、座して動かずにお客さまが自らその情報を話してくれるとは限りません。
そのため、日頃からの対話の積み重ねによって、将来のイベントを予見し、タイミングを逃さずに接触する姿勢が欠かせません。
5.窓口担当者が意識すべきポイント

窓口担当者は、多くの業務を抱えながらも預金推進に取り組まなければなりません。
繁忙期は「待ち時間を短くすること」が優先され、推進の時間を取りにくいのが現実です。
それでも、「少々お時間いただいてもよろしいですか?」といった配慮あるひと言を添えるだけで印象は大きく変わり、次の一手が見えてくる場合があります。
また、チラシ配布や案内カードの設置など、短時間で接点をつくる工夫も効果的です。
6.渉外担当者が取るべきアプローチ

渉外担当者は、融資・預かり資産・新規開拓など多忙な中で推進を行います。
そのため、「時間ができたら預金推進を」と自分に甘く考えると、チャンスを逃してしまうことが多いものです。
訪問営業が難しい共働き世帯が増えるなかでは、企業の職場を訪ねる「職域セールス」が有効です。
つまり、自ら推進の機会をつくり出す能動的な姿勢が、成果を分ける鍵となります。
7.まとめ:金利ある世界における預金推進の再定義
金利上昇局面では、預金は単なる「調達手段」ではなく、金融機関の成長を支える戦略資源です。
また、「地域金融力の強化」でも預金が増えている金融機関とそうでない金融機関の状況を「二極化」と呼ばれるようになり、つまり預金は「信頼のバロメーター」とされつつあります。
お客さまの人生に寄り添い、タイミングを逃さず動機を引き出すことが、これからの預金推進の本質といえるでしょう。
受講期間:2か月
添削:2回(WEB添削のみ)
受講料:9,460 円(税込)
『お客さまに選ばれる 預金獲得力を高めるコース』では、
・なぜ今、預金獲得が求められるのか(背景の理解と腹落ち)
・金利上昇局面における預金推進の考え方(意識の醸成)
・ライフイベントに基づくニーズ喚起の方法(思考の定着)
・お客さまの“動機”や“需要”を引き出す提案トーク(行動への転換)
を体系的に学び、現場で実践できる力を養います。
預金獲得の経験がない行職員でも、具体的な推進イメージがつかみやすく、
「どのように預金獲得を進めればよいか」がわかる内容です。