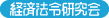秋が深まり、紅葉を見るのによい季節になってきました。寒さが本格的になってくると、石焼き芋が私は恋しくなってしまいます。
「い~しや~きいも~やきいも~♪」というフレーズとともに車で練りまわる、あの車です。
コロナでキッチンカーが増えたこの世の中で、移動販売のルーツになる存在ともいえるかもしれません。
焼き芋は、その歴史を江戸時代までさかのぼるともいわれています。当初は土鍋などで焼かれていて、明治、大正、昭和と焼き芋の文化は続いてきましたが、ファストフードの台頭によって、影を潜めてしまったようです。
ですが、令和の現代では、新国民的スイーツとも呼ばれ、焼き芋が人気になっています。今年の移動販売は今か今かと楽しみにしている今日この頃です。
先月に続き、根菜類のサツマイモが気になってしまい取り上げました。
何かと体調を崩しやすい時期ですので、皆様どうぞご自愛ください。
それでは、11月1日発刊の当社定期刊行誌3誌11月号をご紹介いたします。
『銀行法務21』11月号のご紹介
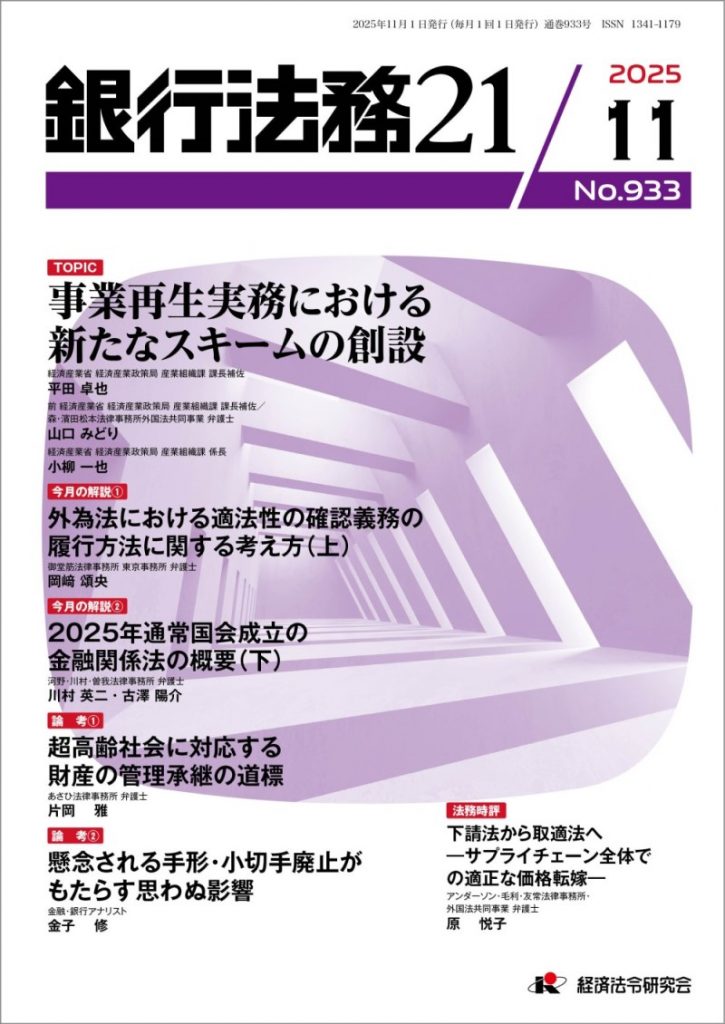
→詳細はこちら
☆TOPIC
事業再生実務における新たなスキームの創設
2025年6月、「早期事業再生法」が成立しました。本法は、倒産前の経営難に陥るおそれのある事業者が、第三者の関与のもと、金融機関等の債権者の多数決および裁判所の認可により、早期での事業再生を円滑に行うことができる制度を創設する法律です。
2本立て企画となる本記事の1では、本法制定の経緯や背景、本法の概要や新しい早期事業再生手続の流れ等について解説し、2では、現行の法的整理手続・私的整理手続との相違点を挙げ、実務上の影響や留意点について整理しています。
☆今月の解説
外為法における適法性の確認義務の履行方法に関する考え方(上)
金融機関において外国送金等の外国為替取引を行う場合に、外為ガイドラインで規定された、外為法上の規制対象取引でないことの確認(適法性の確認)が義務づけられています。
2025年7月、外為ガイドラインQ&Aが改訂され、リスクベース・アプローチによる適法性の確認義務の履行方法に関する考えが明確化されました。
本稿では、適法性の確認義務における、国内から海外に向けた仕向送金を解説。次号(下)では、海外から国内に向けた被仕向送金および国内送金を行う場合に、どのような場面でどのような対応が求められているかを解説します。
☆論考
超高齢社会に対応する財産の管理承継の道標
高齢化・長寿化の進展、単独世帯の高齢者の増加等により、高齢期に向けた資産形成・管理・承継の重要性が高まっています。
本稿では、見直しが検討されている成年後見制度の方向性と実務への影響、プラチナNISAや信託等、高齢者の資産運用や資産承継等の手法などについて概観しながら、今後の商品やサービスの可能性について検討します。
『JA金融法務』11月号のご紹介
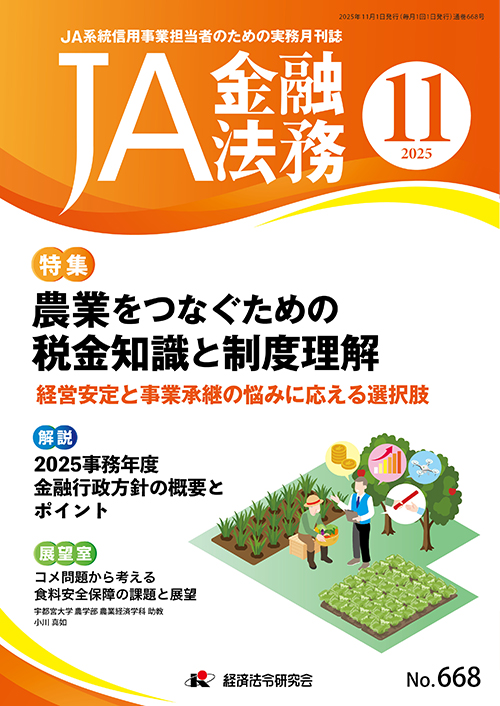
→詳細はこちら
☆特集
農業をつなぐための 税金知識と制度理解
農業経営には、基礎的な税金のほか、様々な税制支援の知識が欠かせません。本特集は、組合員が経営や税金面で抱える悩みやよくある相談事例を紹介。事業承継に有効な税制優遇措置や補助金制度などを解説します。
①よく聞かれる質問で確認しよう 農家の経営・税金相談Q&A
組合員からよく寄せられる農業経営と税金に関する質問を基に、知っておきたい基礎知識を学ぶ記事。税金・税制面を中心とした農業経営に関する内容を、Q&A形式で解説します。
②農業承継に役立つ税制優遇制度
農業承継において有効な税制優遇措置を紹介。暦年課税と相続時精算課税制度、農地を相続したときの相続税の納税猶予制度をメインに取り上げます。
☆取材レポート
魅力あふれるJAを訪ねる(JA滋賀中央会)
実際の農業法人の経営課題を題材にして行う実践型研修により、農業者とのつながり強化と伴走支援型のコンサル力強化を目指す、JA滋賀中央会の取組みを紹介します。
☆解説
2025事務年度金融行政方針の概要とポイント
今年8月公表の「2025事務年度金融行政方針」について、顧客の最善利益義務の遂行、事業性融資、さらなるマネロン対策、金融犯罪対策など、信用事業に携わるJA職員が押さえておくべきポイントを紹介します。
『JA金融法務』11月増刊号『利用者の安全な取引に活かす 金融犯罪の手口と対策』
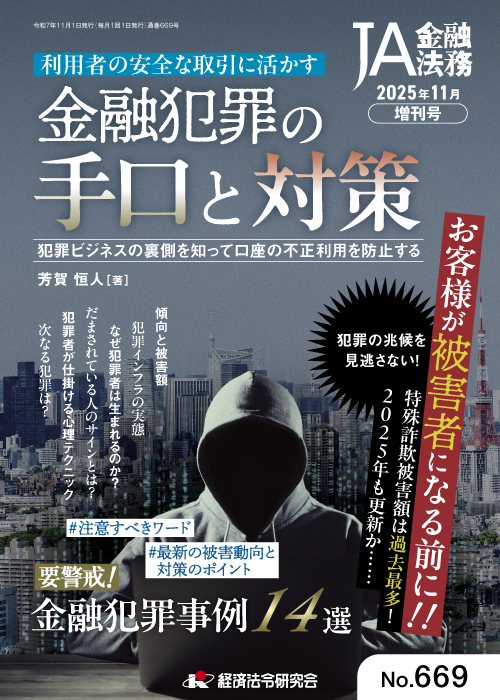
→詳細はこちら
被害の深刻さや、多様化・巧妙化する手口を示すとともに、14の具体事例を通じて、犯罪の動向と対策のポイントを解説。金融犯罪の実態を把握し、兆候を察知する感度を高めます。
『金融・商事判例 №1726/№1727』のご紹介
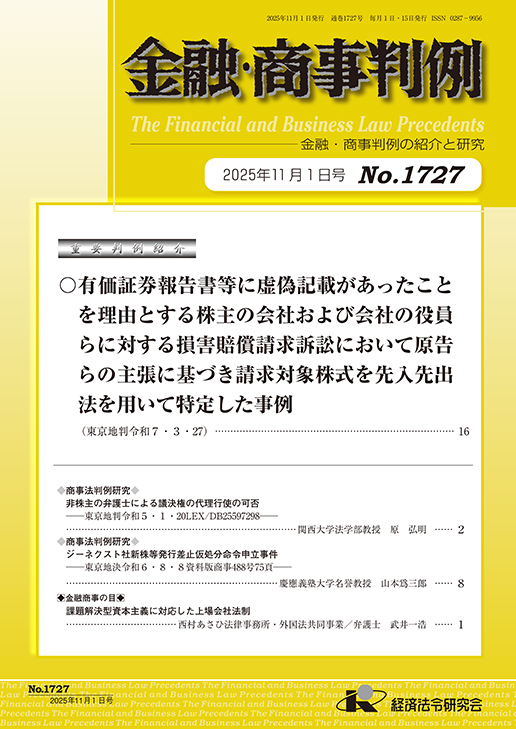
→詳細はこちら
金融・商事判例No.1727(2025年11月1日号)では、
重要判例紹介として、東京地判令和7・3・27の1件の判例を紹介しています。
東京地判令和7・3・27は、有価証券報告書等に虚偽記載があったことを理由とする株主の会社および会社の役員らに対する損害賠償請求訴訟において原告らの主張に基づき請求対象株式を先入先出法を用いて特定した事例です。
巻頭言では「課題解決型資本主義に対応した上場会社法制」について、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業の武井一浩先生にご執筆いただきました。
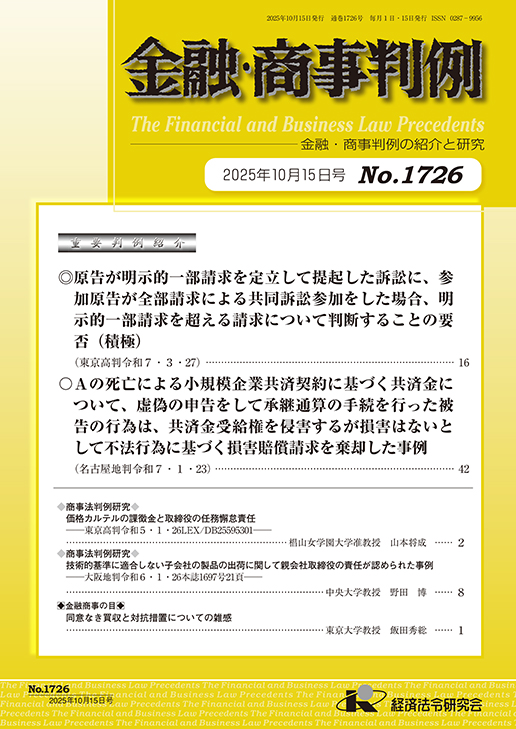
→詳細はこちら
金融・商事判例No.1726(2025年10月15日号)では、
重要判例紹介として、東京高判令和7・3・27、名古屋地判令和7・1・23の2件の判例を紹介しています。
東京高判令和7・3・27は、原告が明示的一部請求を定立して提起した訴訟に、参加原告が全部請求による共同訴訟参加をした場合、明示的一部請求を超える請求について判断することの要否について判断された事例です。
巻頭言では、「同意なき買収と対抗措置についての雑感」として、東京大学教授の飯田秀総先生にご執筆いただきました。
本号も最新情報満載でお届けいたしますので、定期購読のお申込みをお待ちしています。