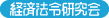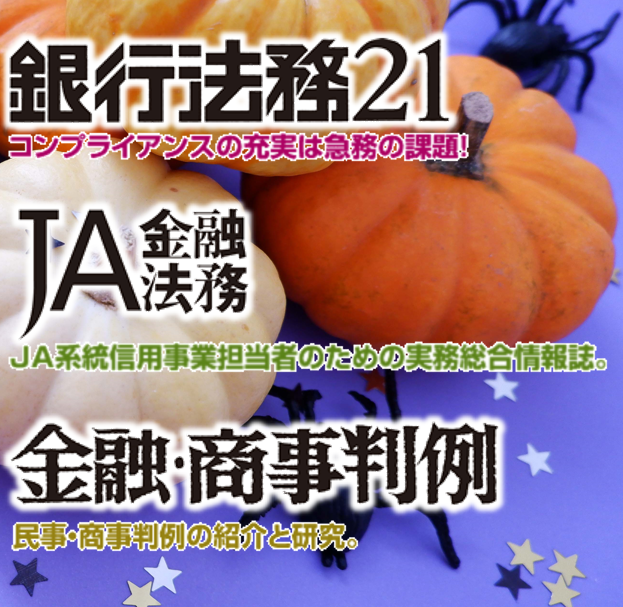
急に肌寒くもなり、街中は半袖の方、長袖の方、半々といったところでしょうか。ちなみに筆者はまだ半袖です。
とはいえ、10月に入ると、なんとなく秋めいて季節の移り変わりを感じます。カボチャやサツマイモなどの根菜類がおいしくなる季節でもありますね。
根菜類は、体を温めるイメージがあると思いますが、すべてが体を温めてくれる野菜ではないそうで、それぞれ特徴があったりします。さらに、調理をすることによって体を温める効果に変化する根菜類もあるようです。
今年はインフルエンザの流行が早く、手洗い・うがいなどの日々の予防や体調を整えることが大切になりそうです。
それでは、10月1日発刊の当社定期刊行誌3誌10月号をご紹介いたします。
『銀行法務21』10月号のご紹介
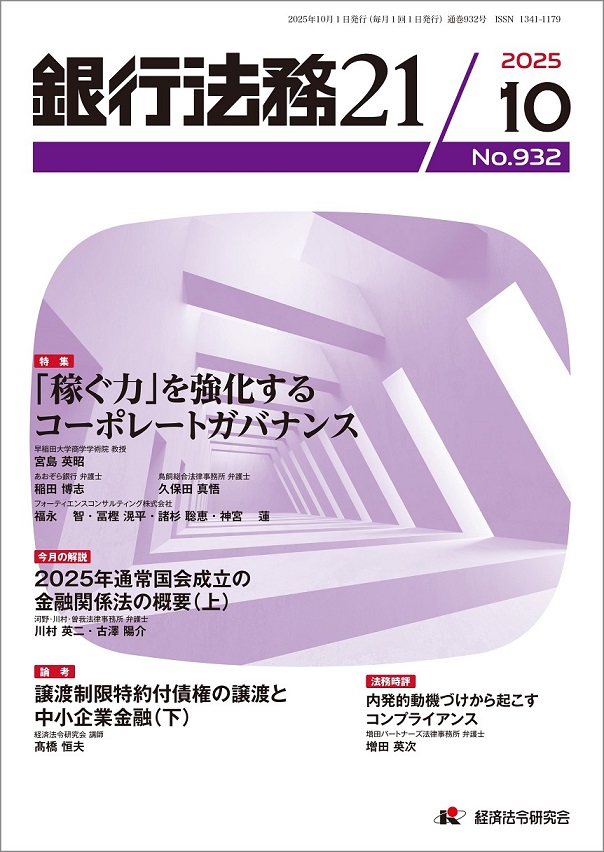
→詳細はこちら
☆特集
「稼ぐ力」を強化するコーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)が適用されてから10年が経過し、社外取締役数の増加、指名委員会・報酬委員会設置の普及など、企業の取組みは着実に進んでいます。ただ形式的な体制整備にとどまっている企業も多いのが現状です。厳しい経済環境を背景に「守りの経営」から、賃上げや成長投資を促す「攻めの経営」に移行し、「稼ぐ力」のさらなる強化を目的に、経済産業省は2025年4月に「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンスガイダンス」を公表しています。
本特集では、コーポレートガバナンスと稼ぐ力に着目して、当該ガイダンスの解説、今後の取組課題、コーポレートガバナンスとPBRの関係性についてご意見いただきます。
☆今月の解説
2025年通常国会成立の金融関係法の概要(上)
2025年の通常国会で成立した金融関係法のうち、上では「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(譲渡担保法)」と「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(早期事業再生法)」の概要と金融実務への影響を解説します(早期事業再生法に関しては、同誌2025年9月増刊号「早期事業再生法と再生実務の要点」も発刊中です)。
☆論考
譲渡制限特約付債権の譲渡と中小企業金融(下)
本稿(下)では、9月号に掲載した上編に続き、将来債権の譲渡および、中小企業金融の円滑化における譲渡制限特約付債権の担保活用の適否や正式担保化について検討していきます。
『JA金融法務』10月号のご紹介
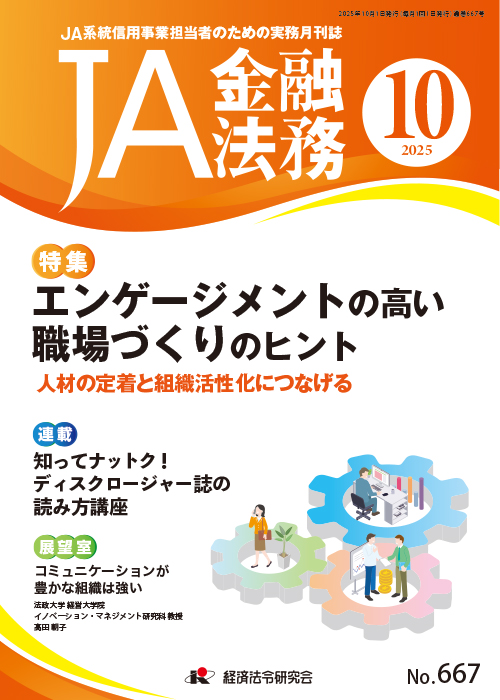
→詳細はこちら
☆特集
エンゲージメントの高い職場づくりのヒント
2023事務年度の金融行政方針において「人的資本」が盛り込まれて以降、人材を資本とした経営への取組みが重要視されています。そこで本特集は、政府が公表する「人的資本可視化指針」においても、人的資本経営の重要な指標の一つとされている「従業員エンゲージメント」に着目し、エンゲージメントとは何かを確認し、その向上のために必要な要素や有効なアプローチ方法を紹介します。
①組織活性化と従業員意識の関係性
エンゲージメントに対する理解を深める記事。定義や注目される背景、高めるべき理由などを整理し、エンゲージメントの視点から、現代の企業(組織)に求められていることを解説します。
②「エンゲージメントサーベイ」の活用法
従業員のエンゲージメントを測る手段の一つである「エンゲージメントサーベイ」に着目。サーベイの仕組みや、実施に向けた準備、実施後の具体的な活用方法について解説します。
③モチベーションをアップさせるチーム文化の作り方
職場の一体感とやりがいを高め、エンゲージメント向上につながる「応援文化」の重要性を解説。その実践的な手法として、「ペップトーク」を紹介します。
④キャリア自律を促す組織の作り方
キャリア自律に対する理解を深め、部下のキャリア支援に役立つ考え方を学べる記事。キャリア自律の必要性、よくある誤解、後押しする社内制度などを基に、個人と組織がともに活性化するヒントを紹介します。
『金融・商事判例 №1724/№1725』のご紹介
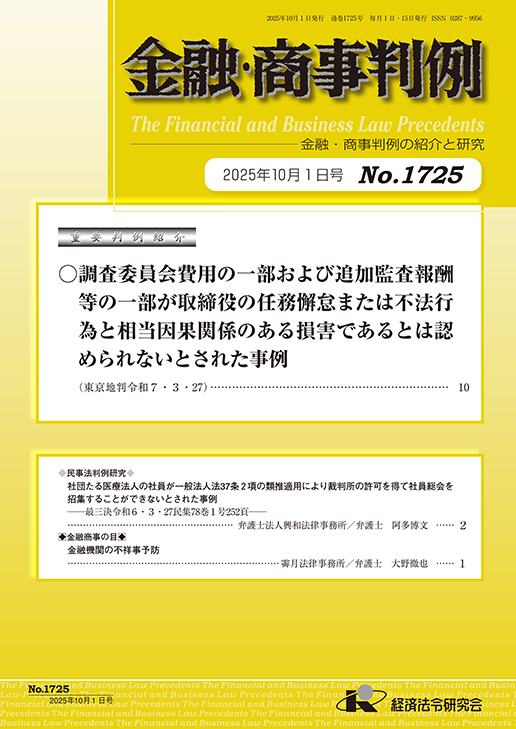
→詳細はこちら
金融・商事判例No.1725(2025年10月1日号)では、
重要判例紹介として、東京地判令和7・3・27を紹介しています。
東京地判令和7・3・27は、調査委員会費用の一部および追加監査報酬等の一部が取締役の任務懈怠または不法行為と相当因果関係のある損害であるとは認められないとされた事例です。
巻頭言では「金融機関の不祥事予防」について、霽月法律事務所の大野徹也先生にご執筆いただきました。
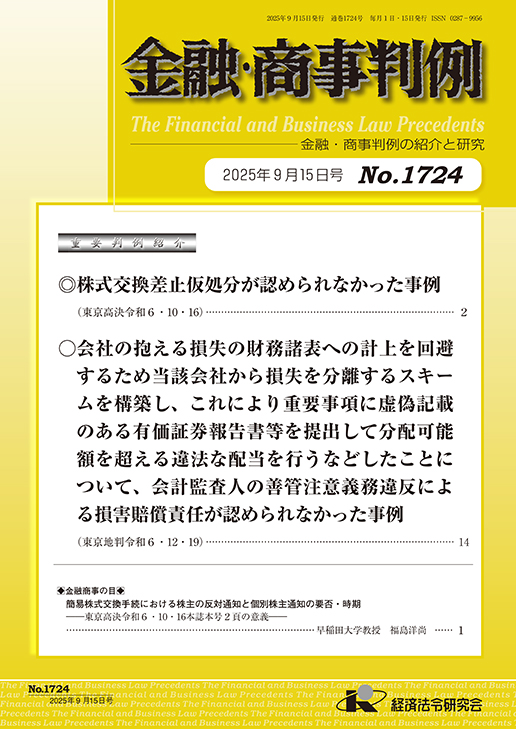
→詳細はこちら
金融・商事判例No.1724(2025年9月15日号)では、
重要判例紹介として、東京高決令和6・10・16、東京地判令和6・12・19の2件の判例を紹介しています。
東京地判令和6・12・19は、会社の抱える損失の財務諸表への計上を回避するため当該会社から損失を分離するスキームを構築し、これにより重要事項に虚偽記載のある有価証券報告書等を提出して分配可能額を超える違法な配当を行うなどしたことについて、会計監査人の善管注意義務違反による損害賠償責任が認められなかった事例です。
巻頭言では、「簡易株式交換手続における株主の反対通知と個別株主通知の要否・時期」として、早稲田大学教授の福島洋尚先生にご執筆いただきました。
本号も最新情報満載でお届けいたしますので、定期購読のお申込みをお待ちしています。