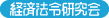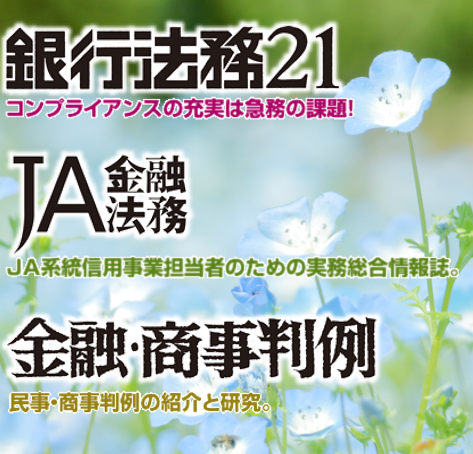
大型連休の中日、桜の季節が過ぎて、いよいよ新緑の季節にやってきました。
「新緑の~」と聞くと、皆様はどのようなことを思いつきますか。
山好きな私は、「新緑の高尾山」という言葉を思い出してしまいます。
最近はだんだんと暑くなり、半袖姿の方も街中で見かけます。そんなときには山に出かけ、涼しい風を全身で感じるのもよいかもしれません。青々とした緑というより、黄緑色に近い色をした木々が生い茂り、山歩きにはよい季節です。
登山者数世界一といわれる高尾山でも、実は遭難が富士山より多いといった情報もあります。いかなる登山の時も、体温調節がしやすいような服装や、登山に適した靴、さらに食料や水分、救急道具などを入れたリュックサックも欠かせません。
大型連休の後半は、全国的に気温は平年並みのようですが、日ごとに天気が変化するようです。
十分に準備して、皆さんお住まいの近くの山々に出かけてみてはいかがでしょうか。
それでは、5月1日発刊の当社定期刊行誌3誌5月号についてご紹介いたします。
『銀行法務21』5月号のご紹介
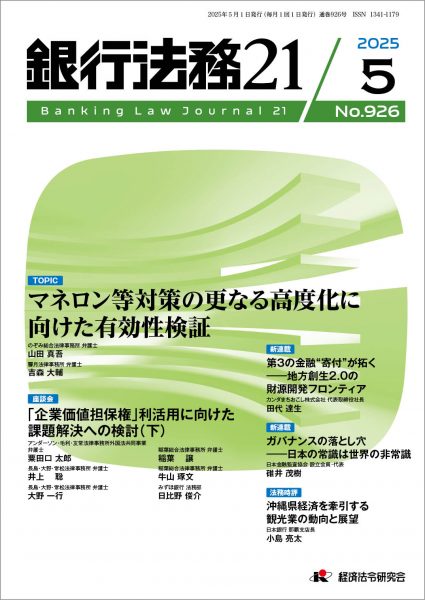
→詳細はこちら
☆TOPIC
マネロン等対策の更なる高度化に向けた有効性検証
金融庁は3月31日に、銀行等金融機関に向けたマネロン等対策の向上のための検査方針である「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」(有効性検証DP)を公表しています。
金融庁は、金融機関等が同庁の要請に応じて実施したマネロンガイドラインに則したリスク管理等の態勢整備が有効に機能しているか、自主的に検証させ、態勢の改善、高度化を促進すべく、今後、両者で有効性検証について対話を行うとしています。
本誌では、有効性検証DPの目的や背景、想定される実施内容、金融庁との対話の手法など、有効性検証DPの内容について解説しています。
☆座談会
「企業価値担保権」利活用に向けた課題解決への検討(下)
座談会の後半となる今号は、企業価値担保権を設定する場合に、どのようなコベナンツを設定し、どのようにモニタリングを行っていくべきかを議論しています。また、倒産手続の際に企業価値担保権がどう評価されるのか、倒産手続時の企業価値担保権の取扱いや実行に関する考え方、留意点を取り上げます。最後に、事業性融資推進法の利用拡大に向け、金融機関等としてどのような取組みが想定されるかなどを検討しています。前号の上編とともにぜひ。
☆新連載
第3の金融“寄付”が拓く――地方創生2.0の財源開発フロンティア
融資・投資に続く「第3の金融=寄付」が地方創生の財源開発手法として注目されています。寄付がなぜビジネスになり得るのか、まちづくりにどう活用できるのか、地方銀行グループ会社で代表を務める筆者が解説していきます。
☆新連載
ガバナンスの落とし穴――日本の常識は世界の非常識
今日、注目を集めるコーポレートガバナンスについて、これまで日本で常識、良いとされてきた取組みなどが実はガバナンス構築の落とし穴になっていることがあります。金融機関を含めた企業のコーポレートガバナンスの課題や弱点を挙げ、解説していきます。
『JA金融法務』5月号のご紹介
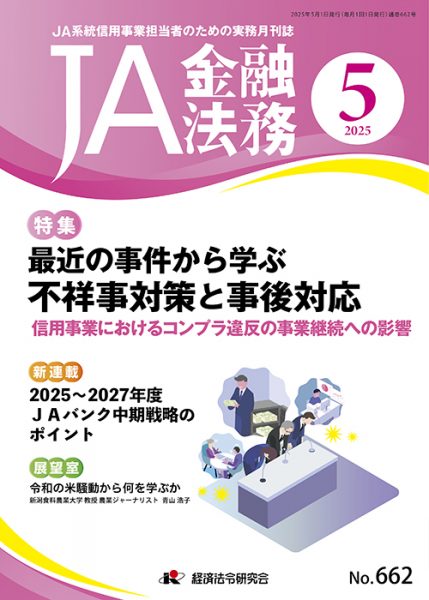
→詳細はこちら
☆特集
最近の事件から学ぶ 不祥事対策と事後対応
不祥事報道が相次いでいますが、JAにおいても、組合員・利用者からの信頼を失うことは組織の存続にも直結する重大な問題となり得ます。
本特集では、不祥事発生時における昨今の企業の社会的責任、不祥事事例分析、事後対応、企業の人権意識、加害者心理など、多角的に対策と対応を解説しています。自組織での不祥事対策の一助にぜひご活用ください。
①近時の不祥事事案にみる企業の社会的責任
情報が瞬く間に拡散される現代において、企業の社会的責任はどのように変化しているのかについて、最近の不祥事事案を基に解説しています。
②調査報告書にみるJA不祥事の発生原因と対策
第三者委員会の調査報告書が公表された実際の不祥事事案から、その発生要因を解説しています。また、それら要因が生まれている真の原因とは何か、またこれを探るための検証事項も示しています。
③早期信頼回復のための不祥事発生後対応の流れ
不祥事が発生した場合、早期に適切な対応を行うことは欠かせません。本稿では、不祥事発生後対応の一連の流れやポイントについて、対応部署の役割とあわせて紹介しています。
④内部通報制度が機能するために必要な「人権感覚」
不祥事の予防策となる内部通報制度を有効に機能させるために重要となる、企業や職員の「人権感覚」について、昨今話題となった様々な企業の不祥事案を参照しながら解説しています。
⑤犯罪心理学から読み解く不祥事加害者の特質
不祥事を起こしてしまう人の心理について、犯罪心理学を基に、発生要因となる環境や個人の心理状態を解説しています。また、これらを踏まえ、犯罪心理学の視点から有効な不祥事防止策を紹介しています。
☆新連載
2025~2027年度JAバンク中期戦略のポイント
2024年12月に公表された「JAバンク中期戦略(2025~2027年度)」について、戦略策定段階・施策実践段階においてJAバンクが提供すべきサポート策を、毎月1テーマずつ、農林中央金庫の所管部署が解説していきます。
『金融・商事判例 №1714/№1715』のご紹介
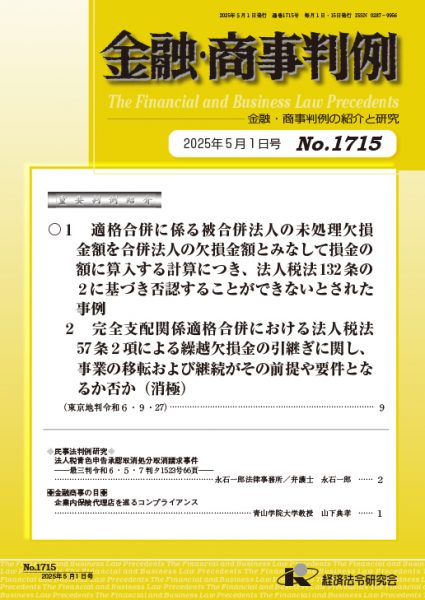
→詳細はこちら
金融・商事判例No.1715(2025年5月1日号)では、
重要判例紹介として、東京地判令和6・9・27の1件の判例を紹介しています。
東京地判令和6・9・27は、適格合併に係る被合併法人の未処理欠損金額を合併法人の欠損金額とみなして損金の額に算入する計算につき、法人税法132条の2に基づき否認することができないとされ、完全支配関係適格合併における法人税法57条2項による繰越欠損金の引継ぎに関し、事業の移転および継続がその前提や要件となるか否かについて消極と解した事例です。
巻頭言では「企業内保険代理店を巡るコンプライアンス」として、青山学院大学教授の山下典孝先生にご執筆いただきました。
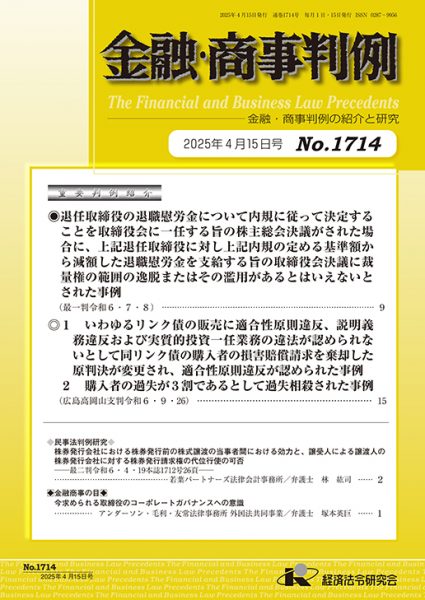
→詳細はこちら
金融・商事判例No.1714(2025年4月15日号)では、
重要判例紹介として、最一判令和6・7・8、広島高岡山支判令和6・9・26の2件の判例を紹介しています。
最一判令和6・7・8は、退任取締役の退職慰労金について内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議がされた場合に、上記退任取締役に対し上記内規の定める基準額から減額した退職慰労金を支給する旨の取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱またはその濫用があるとはいえないとされた事例です。
巻頭言では、「今求められる取締役のコーポレートガバナンスへの意識」として、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業の塚本英巨弁護士にご執筆いただきました。
本号も最新情報満載でお届けいたしますので、定期購読のお申込みをお待ちしています。