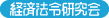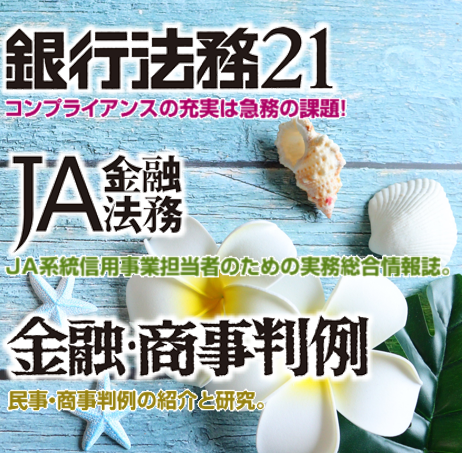
いよいよ、8月、夏本番ですね。
夏場によく行われる盆踊り。特徴的なメロディーを聞くと、どこかでお祭りしているのかなと想像するのではないでしょうか。
文化として根付く風習は、その歴史が古く、盆踊りも例外ではありません。
盆踊りとは、500年ほどの歴史をもち、その名のとおり、お盆の時期に行う行事です。櫓の周りを、円を描くように踊り練り歩く姿が思い浮かびますが、その理由ははっきりしていません。長く続く盆踊りですが、意外にも身振り手振りを大人から子どもに、と代々伝えられてきたために今の今まで残っているようです。
阿波踊り(徳島)、西馬音内の盆踊り(秋田)、郡上踊り(岐阜)が三大盆踊りとして挙げられますが、その土地ごとに盆踊りの姿も少しずつ趣が変わります。例年、次の日程で行われています。
徳島の阿波踊りは毎年8月11日~15日
秋田の西馬音内の盆踊りは毎年8月16日~18日
岐阜の郡上おどりは7月中旬から9月上旬
先週、街を歩いていたらあのメロディーが聞こえてきて、8月のテーマは盆踊りにさせてもらいました。調べていくうちに、「踊って、飲んで、食べて、また踊る!」がキャッチコピーの岐阜の郡上おどりが気になります。夏休みを使って訪れようかと思います。
それでは、8月1日発刊の当社定期刊行誌3誌8月号についてご紹介いたします。
『銀行法務21』8月号のご紹介
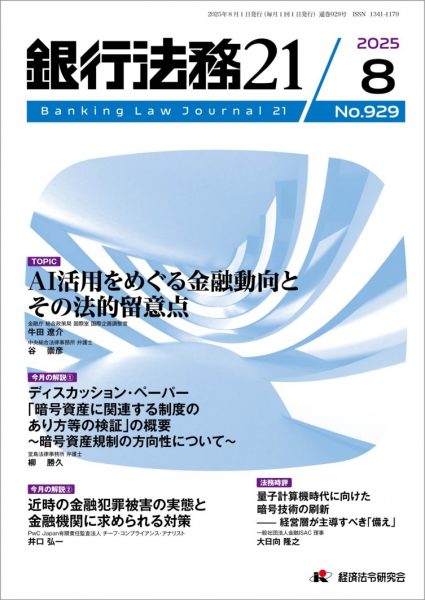
→ 詳細はこちら
☆判決ピックアップ
AI活用をめぐる金融動向とその法的留意点
金融庁は今年3月に「金融機関等におけるAIの活用実態と健全な利活用の促進に向けた初期的な論点整理」として「AIディスカッションペーパー」を公表しました。また、6月には「AI官民フォーラム」第1回を実施し、事務局より実務上の課題が提示されたり、業界団体等の取組事例や課題認識が共有されたりするなど、今後も継続的に開催される予定です。
2本だてとなる本企画の1つ目は、ディスカッションペーパーおよびAI官民フォーラムの資料をもとに、ディスカッションペーパー策定の背景や、従来型AIと生成AIの主なユースケース、AI活用促進に向けた課題等について解説します。
2つ目は、ディスカッションペーパーで提示する実務やガバナンス上の課題や法令上の課題などのうち、金融機関が生成AI活用上の課題として挙げる個人情報保護や知的財産権の法的論点について重点的に解説します。併せて、6月施行の「AI推進法」について、施行された背景、法律の概要、制定後のAI関連指針等の動向について解説し、金融機関実務への影響等も検討していきます。
☆今月の解説
ディスカッション・ペーパー「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」の概要~暗号資産規制の方向性について~
昨今、暗号資産(仮想通貨)に関する規制強化や制度整備が図られていますが、投資被害は後を絶ちません。本ディスカッション・ペーパーは、暗号資産の取引実態を踏まえ、金融庁がこれまで行ってきた暗号資産に関連する制度のあり方等についての検証結果をまとめたものとなります。
本稿では、ディスカッション・ペーパーにおける暗号資産取引の動向や暗号資産取引市場の健全な発展のための制度内容等を解説。特に、暗号資産の規制対象の類型、情報開示・提供規制、業規制やインサイダー取引への対応等を挙げ、各規制の対象の方向性について述べていきます。
☆今月の解説
近時の金融犯罪被害の実態と金融機関に求められる対策
急増する金融犯罪が社会問題化し、マネロン等対策の枠組みを超える面もあり、金融機関においても金融犯罪対策が課題となっている現状です。本稿では、2000年代の金融犯罪の変遷を解説し、金融機関における金融犯罪対策の留意点を整理します。また金融機関の対応が求められる最近の主な当局からの要請について解説します。
『JA金融法務』8月号のご紹介
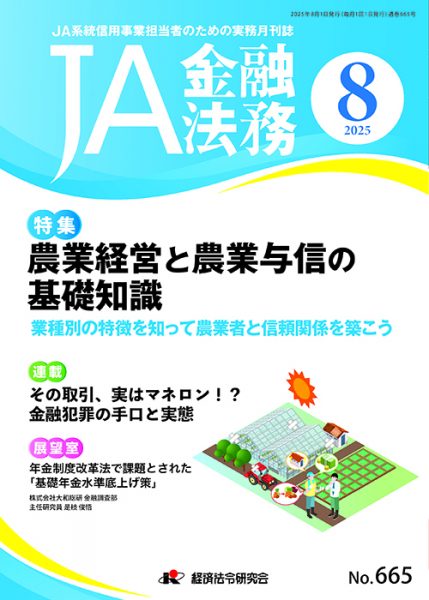
→ 詳細はこちら
☆特集
農業経営と農業与信の基礎知識
JAならではの強みを活かした農業者支援が引き続き求められているなか、事業性融資には慎重かつ的確な判断が必要です。
本特集では、農業融資とその周辺知識に焦点を当て、農家組合員・法人組合員との信頼関係構築に活かせる知識を、初学者向けにコンパクトに紹介しています。業界のビジネスを知り、農業者の経営実態を正しく把握して、適切な与信判断や管理、経営支援に活かすために、ぜひご一読ください。
①業種別農業経営の特徴と資金ニーズ
耕種・畜産における業種別に、必要設備や経営規模の表し方、重要指標などを一覧表で掲載し、どのようなタイミングで資金需要が発生するのか等、農業全体をざっくり見渡します。さらに、与信判断に欠かせない、現地ヒアリングにおいて、すぐに実践できる質問やコメントを例示し、その勘所を紹介しています。
②農業与信と特徴的な税務会計
生産物によって会計処理が異なったり、交付金等が多いという農業の特徴を、耕種農業・畜産農業の例を用いてやさしく解説しています。また、それらの特徴が、個人農業者・農業法人の決算書にどのように反映されているのか、決算書の例をみながら学ぶことができます。
③農業法人の実態把握のポイント
決算書の数値だけでは把握しきれない、真の経営実態を正確に捉えるための、実態貸借対照表・損益計算書の読み取り方や定性評価の視点を解説しています。一見すると破綻懸念先であっても、ランクアップを図り、有効な支援につなげる知識を紹介しています。
『金融・商事判例 №1721/№1720』のご紹介
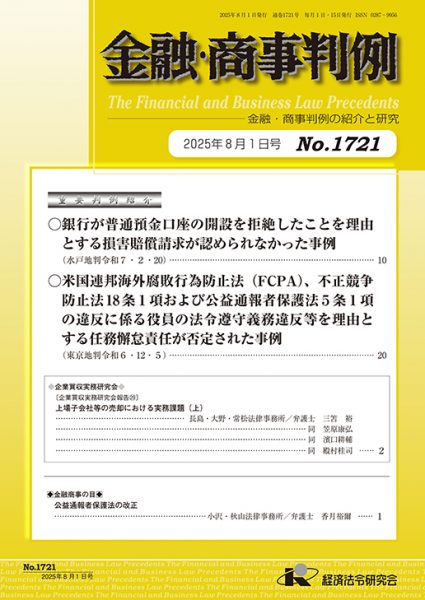
→ 詳細はこちら
金融・商事判例No.1721(2025年8月1日号)では、
重要判例紹介として、水戸地判令和7・2・20、東京地判令和6・12・5の2件の判例を紹介しています。
水戸地判令和7・2・20は、銀行が普通預金口座の開設を拒絶したことを理由とする損害賠償請求が認められなかった事例です。
巻頭言では「公益通報者保護法の改正」について、小沢・秋山法律事務所の香月𥙿爾先生にご執筆いただきました。
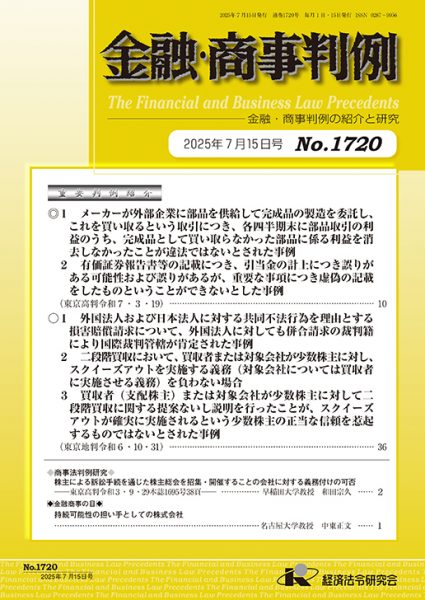
→ 詳細はこちら
金融・商事判例No.1720(2025年7月15日号)では、
重要判例紹介として、東京高判令和7・3・19、東京地判令和6・10・31の2件の判例を紹介しています。
東京高判令和7・3・19は、①メーカーが外部企業に部品を供給して完成品の製造を委託し、これを買い取るという取引につき、各四半期末に部品取引の利益のうち、完成品として買い取らなかった部品に係る利益を消去しなかったことが違法ではないとされ、②有価証券報告書等の記載につき、引当金の計上につき誤りがある可能性および誤りがあるが、重要な事項につき虚偽の記載をしたものということができない、とした事例です。
巻頭言では、「持続可能性の担い手としての株式会社」として、名古屋大学教授の中東正文先生にご執筆いただきました。
本号も最新情報満載でお届けいたしますので、定期購読のお申込みをお待ちしています。