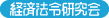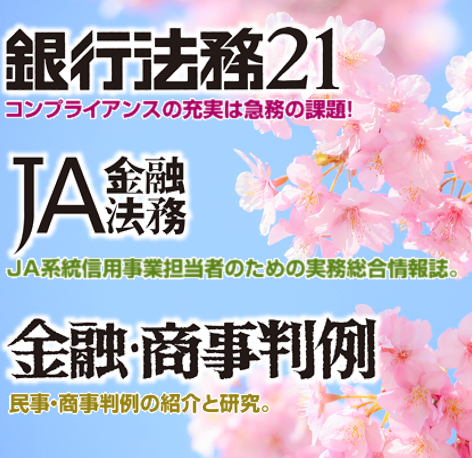
もうすぐ新年度が始まりますね。新年度最初の注目は、なんと言っても4月13日から開催される大阪・関西万博です。
大阪、関西地域からのパビリオンも展開されて、出展者や協賛企業などとして金融機関も名を連ね、地域に根差した金融機関ならでは支援が光ります。
筆者個人として気になるのは、関西パビリオンの「鳥取無限砂丘」です。
鳥取無限砂丘では、その名の通り、プロジェクションマッピングを活用し没入感のある鳥取砂丘が体験できるみたいです。
パビリオン内で実際の砂を敷き詰めた砂丘を体験できて、さらにその床面に虫眼鏡型デバイスをかざして、鳥取の魅力アイテムを探すイベントもあり見逃せません。
鳥取砂丘には幼い頃から行きたいと憧れながら行く機会に恵まれずユーチューブなどで鳥取砂丘の旅行動画が見るだけの日々。
でも、動画だけでは真実に辿り着けない、実際に行ってみないと感じることのできないことがあるように現地に行って体感したい! 真実はいつもひとつ!
少し取り乱しましたが気を取り戻してそれでは、4月1日発刊の当社定期刊行誌3誌4月号についてご紹介いたします。
『銀行法務21』4月号のご紹介
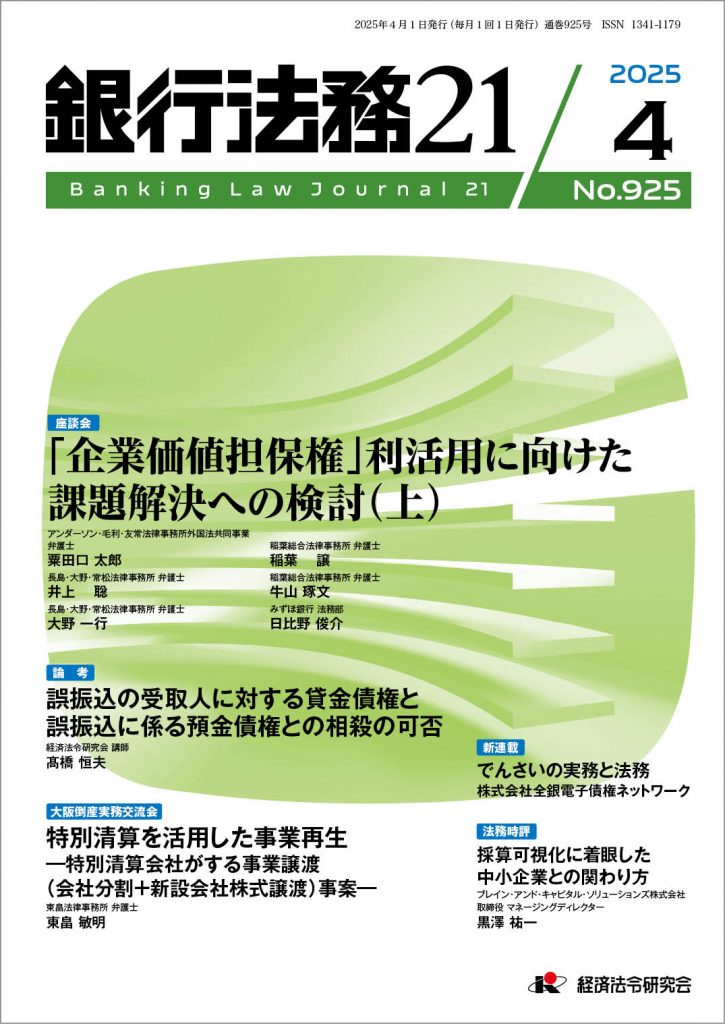
→詳細はこちら
☆座談会
『企業価値担保権』利活用に向けた課題解決への検討(上)
昨年6月、事業性融資推進法が成立し、企業価値担保権制度への期待や議論が持ち上がっています。今回は4月号と5月号のふた月にわたり、本法律の立案関係者ほか金融・ファイナンス・事業再生の専門家である6名の弁護士で座談会を行い、企業価値担保権の課題や活用を中心に議論した模様を掲載します。
今号は、同担保権付き融資の利用が想定される企業について取り上げ、また現状では詳細が明らかになっていない同担保権の与信上の担保評価方法や、本制度活用時に金融機関に期待される役割や課題について検討しています。
そのうえで、同担保権を設定する際に留意すべき点、他の債権や自行以外の金融機関との関わり方など、立案時の想定を含め、現段階でどのようなことが想定されるのか、専門弁護士目線、実務家目線で踏み込んで解説しています。
☆論考
誤振込の受取人に対する貸金債権と誤振込に係る預金債権との相殺の可否
本論考では、誤振込の受取人の貸金債権と誤振込された預金債権との相殺の可否について、参考となる裁判例を挙げ、解説します。誤振込による預金債権の成否、原因関係のない誤振込に係る預金債権の相殺と不当利得の成否、誤振込金に対する差押えと第三者異議などのケースを挙げ、裁判例や学説を検討し、金融機関が留意すべき点を理解します。
☆新連載
でんさいの実務と法務
政府は2026年度末までの約束手形の利用廃止、小切手の全面的な電子化の方針を示し、メガバンクをはじめ、紙の手形・小切手の発行終了を発表しており、でんさいサービスやインターネットバンキングの利用を促しています。一部報道によると約8割の信用金庫がでんさいネットが提供する「でんさいライト」を導入するなど、手形・小切手の全面電子化に向けた取組みが拡大しています。本連載は、でんさいの基本を押さえ、金融機関の実務と法務の両面から解説します。
『JA金融法務』4月号のご紹介
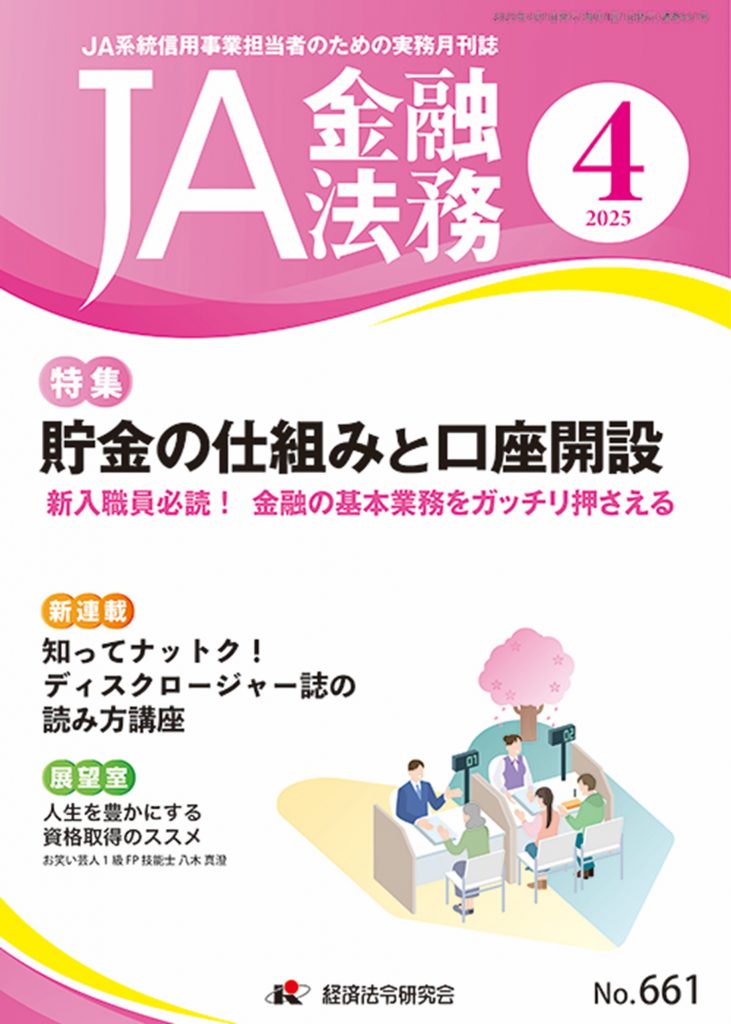
→詳細はこちら
☆特集
貯金の仕組みと口座開設
高齢化等による組合員の減少や貯金流出が課題になっているところ、貯金の確保に向けて、その役割が改めて注目されています。
そこで、本特集では、貯金の役割や種類などの基礎知識を整理し、業務の基本である口座開設の流れや注意点を解説。また、本人確認書類の確認すべき点等も紹介していますので、対応の留意事項のアップデートにご活用ください。
①貯金の基礎知識と口座開設の流れ
お客様やJAにとって、貯金とはどのような役割をもつのか、また、その仕組みや商品の種類などを解説しています。さらに、口座開設(普通貯金)の大まかな流れに沿って、各手順における対応のポイント、声かけ例も学ぶことができます。
②本人確認書類の種類とチェックポイント
口座開設時に必要な本人確認書類について、よく利用されるものを抜粋し、各書類の見本写真付きで扱いの留意点を解説しています。現在は使用できる書類、これから変わる書類なども整理することができます。
③こんな時どうする? 迷いがちな口座開設Q&A
代理人や未成年者、外国籍の方からの口座開設依頼など、注意が必要なケースについて、Q&A形式で解説しています。確認すべき事項やその対応方法など、押さえておきたいポイントをまとめた学習記事です。
☆新連載
知ってナットク! ディスクロージャー誌の読み方講座
ディスクロージャー誌を目にした取引先や組合員から、自JAの経営状況などを質問された際の返答を例に、なぜそのような疑問が生じるのか、説明のポイントなどをわかりやすく解説。毎月1つずつ、ディスクロージャー誌に掲載されている項目を読み解いていきます。
『金融・商事判例 №1711/№1712/№1713』のご紹介
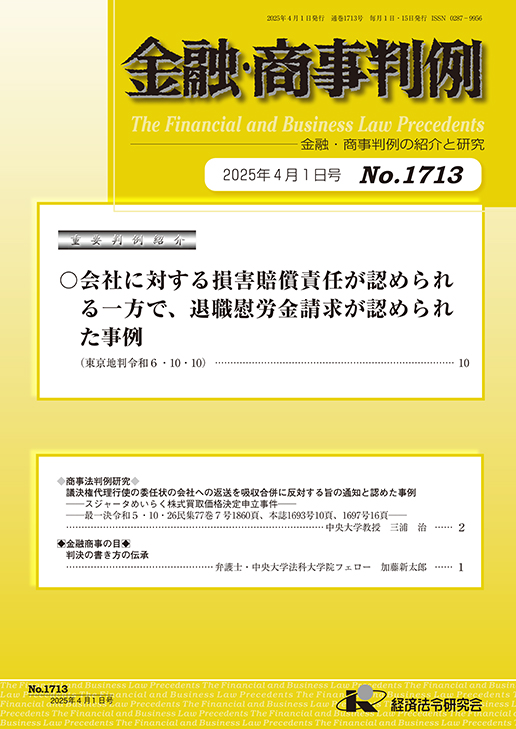
→詳細はこちら
金融・商事判例No.1713(2025年4月1日号)では、
重要判例紹介として、東京地判令和6・10・10の1件の判例を紹介しています。
東京地判令和6・10・10は、会社に対する損害賠償責任が認められる一方で、退職慰労金請求が認められた事例です。
巻頭言では「判決の書き方の伝承」として、東京高等裁判所部総括判事を務められ、現在、弁護士・中央大学法科大学院フェローの加藤新太郎先生にご執筆いただきました。
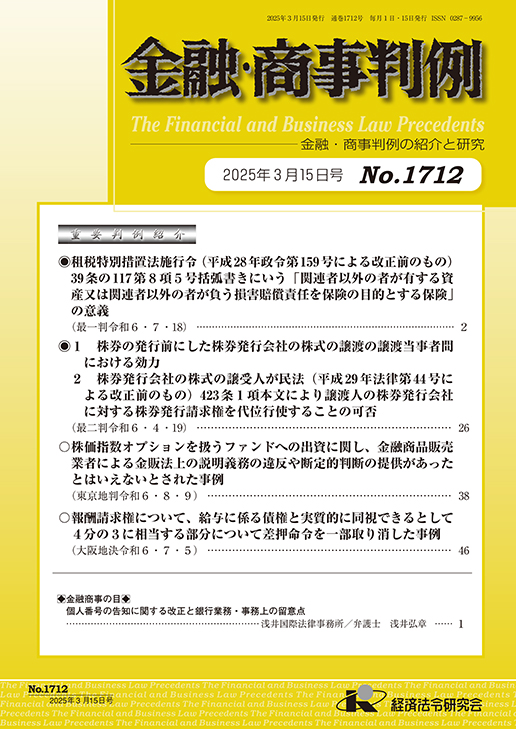
→詳細はこちら
金融・商事判例No.1712(2025年3月15日号)では、
重要判例紹介として、最一判令和6・7・18、最二判令和6・4・19、東京地判令和6・8・9、大阪地決令和6・7・5の4件の判例を紹介しています。
最一判令和6・7・18は、租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」の意義について述べた事例です。
巻頭言では、「個人番号の告知に関する改正と銀行業務・事務上の留意点」として、金融機関の実務に与える影響について、浅井国際法律事務所の浅井弘章弁護士にご執筆いただきました。
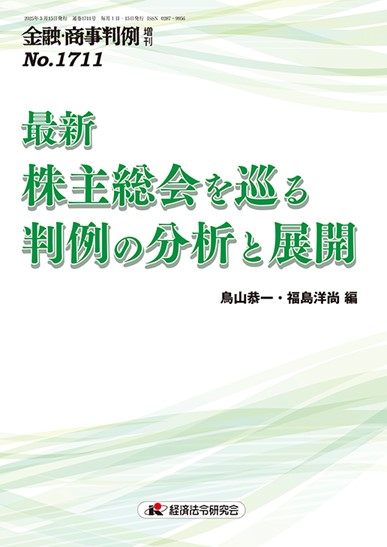
→詳細はこちら
金融・商事判例No.1711(2025年3月増刊号)では、
「最新 株主総会を巡る判例の分析と展開」と題し、早稲田大学教授の鳥山恭一先生、福島洋尚先生を編者に迎え、令和になってから示された株主総会を巡る注目すべき最新判例を学者の先生方に解説いただきました。
招集手続・少数株主による招集等、運営、株主提案、議決権行使、採決・決議要件、決議の瑕疵・決議の効力、訴えの利益の分野で構成しています。
本号も最新情報満載でお届けいたしますので、定期購読のお申込みをお待ちしています。